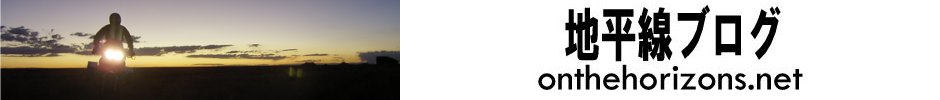XRV750のフロントタイヤはチューブタイプなのでパンクすると瞬く間に空気が抜けてしまい走行不能となり、その場で修理が必要になる。
リヤタイヤであればセンタースタンドで浮かすことができるけれども、フロントはそうもいかず、なにかで車体を支えてやらねばならない。例えばパニアケースだったり、落ちている石やコンクリブロックだったり。たいていなんとかなる、かな。最悪横倒しにすればいいかなとおもっているので特にそれ専用の道具は持ち歩いていない。あれば便利なのだろうけど。
30年ちかくオートバイに乗っているけど出先でフロントタイヤがパンクしたのは2、3回しかない。
今回の例は南米のベネズエラ北部のマラカイボという街の郊外で、バイパス路を走行中に突然出現した道路の凹みにタイヤを強烈にぶつけてしまい、リム打ちによるパンク。周りの流れに合わせていたので時速100キロ以上は出ていたところ、前走車の下から突然現れたギャップは避けれなかった。両手がしばらく痺れたほどの衝撃だった。
よくコケなかったものだ。あとから気が付いたけどフロントのリムも凹んでました。(南米に限らず、外国では幹線道路でもよく大穴が空いてます)
速度なのか衝撃からか、パンク直後もなかなか停まれなかったせいなのか、チューブはパックリと裂けるように破れており再利用不可だった。そこで現地で買っていた(たしかブラジルのアマゾン河流域の町、ベレンかマナウスのお店だったかな)予備チューブを使ったのだけれど、これがマズかった。
メーカー不明の、たぶん中華製のナゾの素材でできた、タイヤチューブというよりはプールで使う浮き輪が分厚くなったような感触のモノ。しかも新品なのに穴空いてるし。まずその穴を塞ごうとするも、手持ちのパッチや糊ではうまく接着せず、修理できたと思っても空気圧をあげて走り始めると糊が剥がれてまた修理、、を日を跨いで7、8回繰り返し、手持ちの糊もパッチも残りわずかになった翌日の昼頃、なんとか宿にたどり着けた。
その途中、道端の空き地でパンク修理しつつテントを張って一晩過ごしたり、

作業中に通りがかった警察官に道端では危険だから、と警察署の敷地内まで案内誘導してもらい修理作業させてもらったり(みな気持ちのよい男たちでした)、

治安よろしくない街で何度も慌てて作業したせいか、最後は携行エアポンプもゴムのパッキンまで擦り切れて使用不能になりヒヤヒヤだった。(この時持っていたDRCの樹脂でできた足踏み式エアポンプは人力でもラジアルタイヤのビードをあげられたのでお気に入りだったのだけど)
結局宿からタクシーでタイヤリペア工場に行き、直してもらいました。ちなみにプロの彼らもはじめはコールドパッチで修理してたけどうまくいかず、さいごに「ホットパッチ」使ってようやくチューブとして使えるように。ホットパッチなんてはじめて見たよ。
教訓
予備チューブはちゃんとしたモノを。
修理用のパッチは大き目のモノを。
エアポンプも信頼性の高いモノを。
修理用の糊(セメント)も十分に持とう。
ところで最近流行りのチューブレス車でもリムが変形するほどの衝撃だとその場で修理不可だと思うよ。